|
|

ラドールと言う石膏粘土製です。
人形師という人に惹かれて、初めて作ったものです。心の師、川本喜八郎先生(人形師の手ってどういうものかと握手してもらいました。)の言葉「人形のことは人形にきけ」という教えに従って四谷シモン先生の学校に行って先生や生徒の人と話したり、関節人形を入手したり、ビスクドールを収集したりしていたら、何時の間にか人形の魅力の虜となり、現在本末転倒状態。(笑)
それでも設計図を描いて粘土をこねて、初めて作ったときは感動したものでした。何の形もない土くれに形を与えることってこんなにも感動するものかと感じましたよ。これが後に造られる私の原型作品。これを造るにも3ヶ月掛かりました。この頃は人形の材料がどこに売っているのかも判らず、難儀致しました
 |
|
|
|
|
|

やはりラドール石膏粘土製です。
始めの作品より、少し小さい子。この子を作ったとき、殆ど夜の作業だったのですが、人形は夜造るものだと、しみじみ思いました。薄暗い電灯の下で、静かな時間の元、古いビスクドールの見守る室内、コーヒーの匂いを漂わせた空間での作業。不思議を造りたいなら、夜がいい。
この子は近くの雑貨屋さんに少し飾ってもらいました。人の意見を聞きたくて、置かせてもらったのですが、作品というものは、人の性格をを反映するもので、(手紙の字でもそうですが)男性の作品らしいといわれ、ショックを受けました。男女の雰囲気をも作品には盛り込まなければ、良い作品などはできやしないのじゃないかと・・・。(四谷シモン先生の人形は先生にそっくりの雰囲気で、人の考えはそれぞれだともおもいますが)
 |
|
|
|
|
|

この子を作ったとき、近くの雑貨屋さんが不況には勝てず、潰れてしまいました。この店では、他の人形製作者とも話をしたりして、人形製作のサロンのような場所だったのですが、残念な事です。どこか近場で展示してくれる場所ってないかな。
1体造るのに3ヶ月も掛かっているのは、時間の使いすぎだと思い、2体目の作品を型取りして、時間の短縮を計りましたが、やっぱり時間はかかるものです。こう言うものって大量生産には向きませんね。全然駄目です。この子には自分でデザイン、注文した洋服を着せています。人形製作はこれ以来休止状態になってしまいました。人形師に憧れて、人形の製作を共に語ろうという人、いませんかね?私の前からは誰もいなくなってしまいました。残ったのはこの3姉妹だけで、なんか寂しい限りです。
 |
|
|
|
|
|
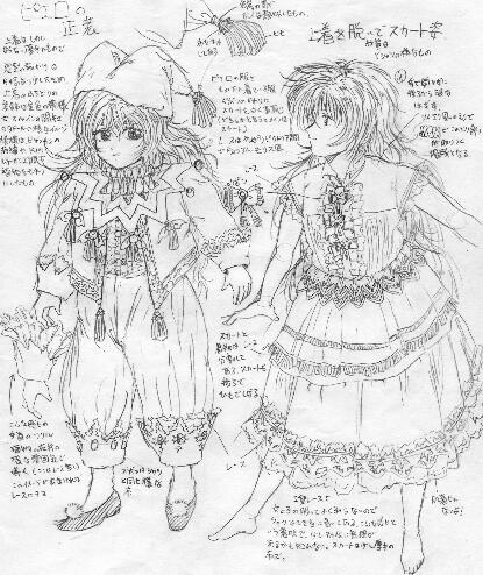
服のデザインです。ピエロ人形用のものですが、人形のイベントに参加していて、作ってもらえそうなサークルにお願いしたら、出来ないと言われまして、それで前写真の様な服に変更しました。この子のイメージが現在のトップ絵を飾っています。
実は、服のデザインにも男のデザインか女のデザインか雰囲気で判るのかなと考えて、聞いてみたのですが、そんな事は無さそうです。ピンクハウス系のフリフリ服を男性がデザインしている、なんて聞くと、イメージが壊れてしまいそうな感じがしませんか?でも海外のファッションショーのデザイナーって男性を良く見かけますよね。
今はちょっと休止中ですが、またいつか人形製作を始めたいと思ってます。
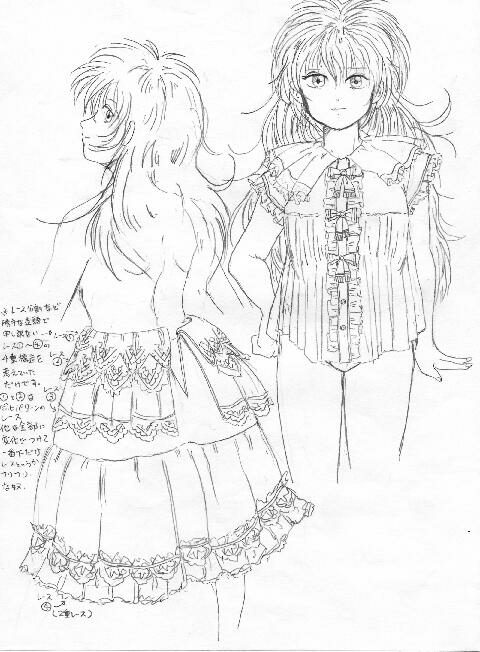 |
|
|
|
| tete jumeau S・F・B・J paris11 |
|

1842年〜1899年(後にSFBJに吸収)
ジュモウ親子による工房。ビスクド−ルの世界においては代名詞のような工房。
ピエールジュモウは1842年にパリのサール・オ・コントにマダムベルトンとともに工房を開き、2年後のパリ工業博覧会で賞を受け、47年に後独立。
55年、パリ博・ロンドン博で賞を受け、人形、衣装、ヘッドの制作を全面的に広告するようになる。
1873年パリ郊外に陶製ヘッド工場を建ててからジュモウの名は広く知れ渡り、76年に息子のエミールもウィーン博・フィラデルフィア博等で金賞を受賞し、ピエールは息子に後を譲ることになる。
エミールジュモウは人形作家として数多くの業績を残している。持ち前の独創性と父の技術を受け継ぎ、78年以降人形に爆発的な変革をもたらす。パリ万博で堂々の金賞を受賞し、スリーブアイ、フーチングアイ、胸にふいごを仕込んで「ママ」と声を発するなど多くのパテントを取得、人形作家の第1人者と称されることとなる。フランスで花開いた人形の黄金期である。
ジュモウの作品は特徴的な眉と睫毛、明るい頬等一目でそれと判断でき、ベベ、テート、トリステ、ポートレート等数々の人形を世に送り出し、100年以上経った今でも絶大な人気を博している。
しかし、安価なドイツの人形に市場は推移してゆき、1899年にフランスの各工房はこれに対抗する形でフランス人形玩具共同組合(SFBJ)を結成、時代の中でジュモウ工房も解体してゆく。
ドイツ人形ばかり収集していた私にとって、初めてのフランスの子、SFBJのジュモウ。目の深さがドイツの子とは全然違い美しい。100年近く経っているのにとてもきれいな子。
 |
|
|
|
| A made in Germany169(kestner) |
|

1805年〜1925年
J・Dケストナーによる人形メーカーはドイツ最古の工房。
陶磁器の一大生産地として栄えたドイツでは、フランスと変って素材の供給地としての役割を担っていた。人形の総合メーカーであるケストナ−は、ペーパーマッシュを素材とする人形から制作を始め、他のフランス工房にヘッドの供給をしたりしながら技術を磨き、キッド製のボディ、コンポジションドールの傑作を次々に生み出す事となる。
1900年代になると、フランス人形とは趣を異にしたキャラクタードールの制作に力を注ぐ事となり、ケストナー色の濃い独自の人形を作り出していく。
この頃にはフランス人形工房は衰退し、アメリカ輸出品としてもドイツ人形が隆盛を究めている。
しかし、ドイツ人形の黄金期も束の間、第一次世界大戦の波の中で、ドイツ商品の輸出は減退を余儀なくされ、本国ドイツで作られつづけた人形達は、戦火の中で少女達に夢を与えつづけた。
戦後に一時復活したかに見えたドイツの人形業界も、新しい時代の動きの中、特に荒れ狂ったファシズム運動の下で生産を脅かされ、1920年代後半に次々と姿を消していき、ケストナー社も時代に埋もれるように、工房の歴史に幕を閉じることとなった。
ドイツのちょっと小さめのケストナー。ガラスの目が印象深い子。この子の様な顔って、見ていて魅力光線でも出しているみたいに引き込まれてしまいます。 |
|
|
|
|
|

1865年〜1925年
コッペルスドルフに磁器工房を創設したアーモンドマルセルは、1890年に人形のヘッドを造り始め、1894刻印のある初期作品は人気を博し、数年に渡って制作されつづけた。他の人形工房にもマルセル社のヘッドは供給されボディは他社という形で販売されている。
1904年に息子のアーモンドマルセルJrがアメリカ入学の内にセントルイス大賞を受賞することで、アメリカでの需要が拡大、代表作、特にモールドに390シリーズは大ベストセラーとして制作され続けた。
しかしながら、第一次世界大戦によるドイツ人形産業の衰退により、これを打開するべく1924年に独自のベビードール、後のベビードールの元祖を制作するも、努力空しく翌年には工房閉鎖を余儀なくされた。
彼の出身は一説にはロシア人とも言われる。
これはアーモンドマルセルのロングセラー390。全てオリジナルの衣装、とても整った顔立ちの美人な子。前の持ち主の話では、元、オタワ博物館に50年間収蔵されていたもので、収蔵番号が刻印されている。博物館の子が手に入るなんて幸運でした。
 |
|
|
|
|
|

ドイツの代表的な工房、シモンハルビックのヘッドにカマー&ラインハルトのマーク。購入当時洋服が下着しか無かったので、服を着せてあげました。小さめの子。
 |
|
|
|
| Germany HEINRICH HANDWERG SIMON&HALBIG 2 1/4 |
|

ドイツの工房、ハインリヒハンドベルグとシモンハルビックの作品。オリジナルドレスにオリジナルのペイント。ビスクにヘアラインなどは無し。髪は交換されている。55cm
ボディに赤くハインリヒハンドベルクのスタンプ有り。 |
|
|
|
| C M Bergman Walterhausen 1916 8 |
|

ドイツの工房、ベルグマン社製。この頃は第一次世界大戦の影響で、ドイツのビスクドールが衰退したじきにさしかかる。
服と髪は新しく交換済み。ボディはリペイントされている。約60cm。
私が最初に入手したのがこの子だった。
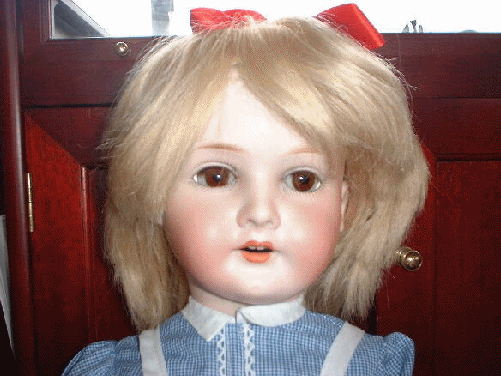 |
|
|
|
|
|

メーカー不明なドイツのビスクドール。
約50cm。髪と服は新しい。 |
|
|
|
|
|

やまと社のビスクドール。
第一次世界大戦の煽りを受けて、ドイツ製のビスクドールが入手困難になったため、日本製が輸出される様になったものである。
元々、市松人形などのノウハウがあったためか、日本製品の西洋人形も受け入れられていたが、戦争が終わってドイツ人形が復活すると供に、製作もされなくなってしまった。
大正時代のほんの一瞬の間に作成されて、海を渡った子である。 |
|
|
|
|
|
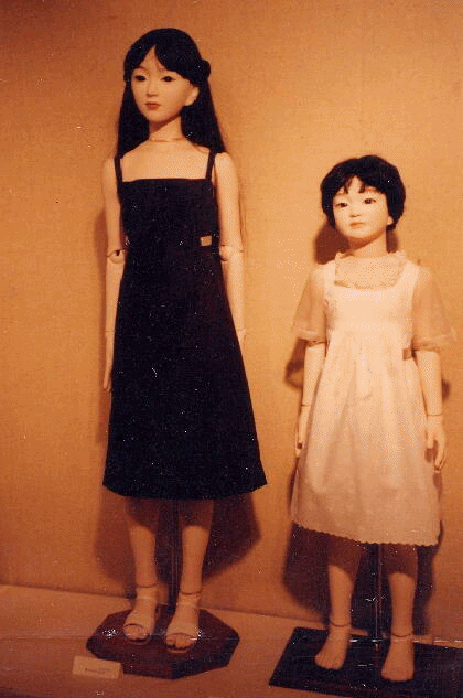
3月に行われている、エコールド・シモン人形展で見つけた子。
新宿の紀伊国屋書店で出会い、その時は入手するべきか迷った挙句、写真を撮って帰ったのだが、写真を見て入手を決めた。(黒い服の女の子の方)
シモン人形学校に連絡して、作者と会う機会を設けてもらいました。90cmはある胡粉製の大きな子。
作者曰く、「服はあくまでオプションで、本当はいらないものです。」服は作品の造形美の邪魔だと語っていました。
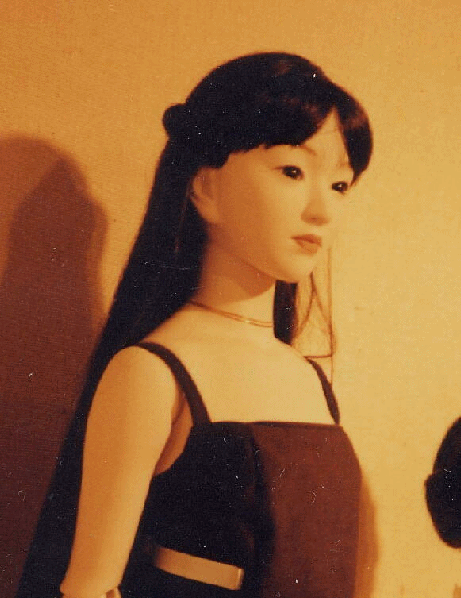 |
|
|